小中学生の近視の正確な実態や生活習慣との関係を明らかにするため、文部科学省が令和3—5年に「児童生徒の近視実態調査」を行いました。これまでのデータでは児童生徒の裸眼視力が低下していることは把握できても、その原因が判りませんでしたが、今回の調査は屈折計や眼軸長(眼球の前後径)測定装置を用いた本格的な調査となりました。今回は「令和5年度児童生徒の近視実態調査事業結果報告書」の内容をお伝えしたいと思います。
|
調査の概要
|
| 実施期間 : |
令和5年4月〜7月 |
| 対象者 : |
検査受検者数 8,417名 |
|
光学式眼内寸法測定装置とレフラクト・ケラトメータを用いて眼の状態や屈折の状況を測定。 |
| 調査項目 : |
370方式視力測定法による視力測定(裸眼視力、矯正視力)「A(1.0以上)」「B(0.9-0.7)」「C(0.6-0.4)」「D(0.3未満)」
および生活アンケート、学校アンケート |
|
|
主要な調査結果 |
|
裸眼視力判定の分布(図1-1、1-2) |
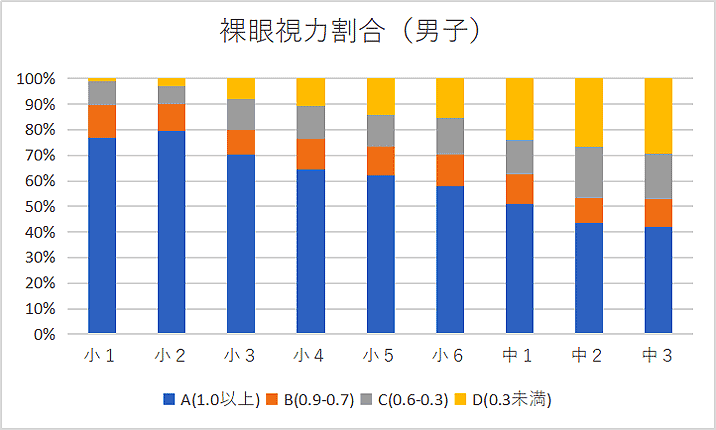 |
図 1-1
|
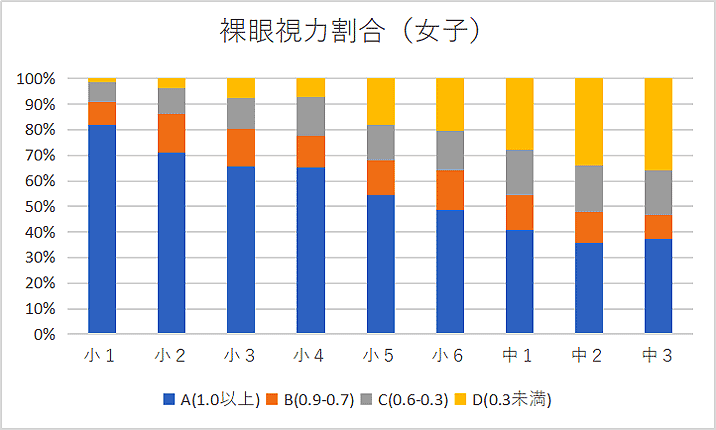 |
| 図 1-2 |
|
| 小学生: |
全体的に「A(1.0以上)」判定の割合が高く、右眼3,618名、左眼3,516名でした。 |
| 中学生: |
小学生と比較して「D(0.3未満)」判定の割合が大幅に増加しており、右眼974名、左眼970名でした。これは、学年が上がるにつれて視力不良者の割合が増加していることを示唆しています。
|
|
眼軸長の分布(図2-1、2-2) |
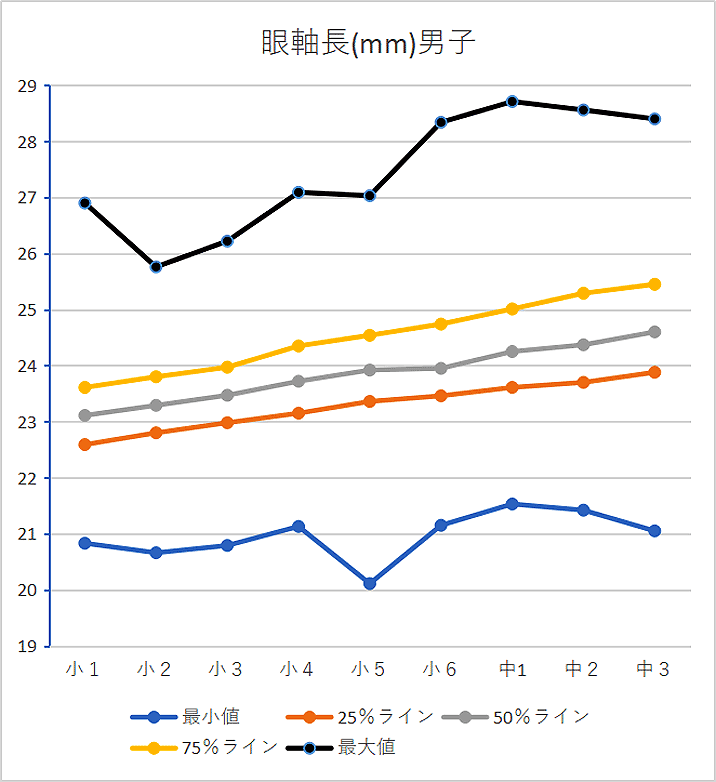 |
図 2-1
|
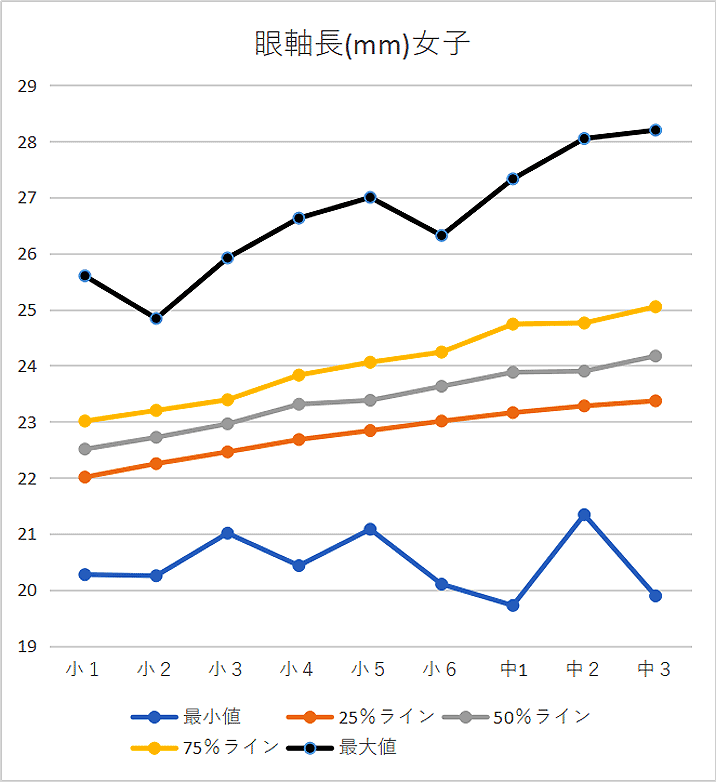 |
| 図 2-2 |
|
学年が上がるにつれて平均眼軸長が伸びる傾向が見られました。小学1年生男子の平均眼軸長(右眼)は23.01mmに対し、中学3年生男子の平均は24.66mmでした。小学1年生女子の平均眼軸長(右眼)は22.30mmに対し、中学3年生女子の平均は24.17mmでした。
「小学1年生の正常な眼軸長はおおよそ22〜23mmで、成人までにおおよそ23〜24mmとなる」と説明されており、児童生徒の成長に伴う眼軸長の自然な伸びと、近視進行による過剰な伸びの両方が考えられます。
|
眼鏡・コンタクトレンズについて |
眼鏡またはコンタクトレンズの使用
学年が上がるにつれて、眼鏡やコンタクトレンズの使用割合が増加しています。
特に中学生では、眼鏡のみ使用、眼鏡およびコンタクトレンズ使用、コンタクトレンズのみ使用の合計が男子で3年生で約43%、女子で3年生で約53%に達しています。
|
アンケート結果から |
休み時間の屋外利用頻度
学年が上がるにつれて「ほとんど外に出ない」の割合が増加し、特に中学生では男子で約43%〜50%、女子で約66%〜79%が「ほとんど外に出ない」と回答しています。
|
授業・休み時間以外の屋外利用時間
学年が上がるにつれて「30分未満」の割合が増加し、小学生高学年から中学生にかけては特に女子で屋外活動時間が短い傾向が見られます。
|
学校以外での勉強や読書の時間
学年が上がるにつれて勉強や読書の時間が長くなる傾向が見られ、中学生では1日あたり「90分以上120分未満」や「120分以上」の割合が増加しています。
|
学校以外でのPCやタブレット使用時間
学年が上がるにつれてPCやタブレットの使用時間が長くなる傾向が見られ、特に中学生では「120分以上」の回答が男子で約12%〜18%、女子で約8%〜11%と一定数存在します。
|
スマホ、携帯ゲーム機等の使用時間
学年が上がるにつれて使用時間が長くなる傾向が顕著で、特に中学生では「120分以上」の回答が男子で約34%〜51%、女子で約29%〜47%と非常に高くなっています。
|
PCやタブレット、スマホ・ゲーム機使用に関する目を休めるためのルールの有無
学年が上がるにつれて「ルールは決めていない」または「決めたがあまり守れていない」の割合が増加しています。中学生ではPC/タブレット利用で約70%〜83%、スマホ/ゲーム機利用で約61%〜80%がルールなし、または守れていないと回答しています。
|
|
考察と示唆 |
|
近視進行の実態 |
| 裸眼視力1.0未満の割合、特に中学生における「D(0.3未満)」判定の増加は、児童生徒の近視進行が深刻な問題であることを明確に示しています。眼軸長の学年ごとの伸びも、近視の軸性近視への進行を示唆するものです。
近視は、メガネなどで矯正すれば視力がでるものとして、これまであまり問題視されてきませんでした。しかし、さまざまな疫学データの蓄積から、近視が将来の目の病気のリスクを高める可能性があることが分かってきています。
|
|
屋外活動の減少 |
| 休み時間や授業・休み時間以外の屋外活動時間の減少は、近視進行の一因として示唆されています。台湾の事例では、屋外活動2時間の確保が視力改善に繋がったことが報告されています。複数の研究結果から、1日2時間以下の屋外活動でも近視の進行抑制に効果が得られる可能性が示唆されています。このため、1日2時間に満たなくとも、なるべく多くの時間を屋外で過ごした方が、近視抑制の観点からは望ましいと考えられます。ただし、外で過ごすに当たっては、熱中症や紫外線などの影響にも配慮する必要があるため、強い光を避け、なるべく木陰や建物の影で過ごすとよいでしょう。
|
|
近業時間の増加 |
| 勉強・読書、PC/タブレット、スマートフォン/ゲーム機などの近業(近くで物を見る作業)時間の増加が顕著であり、特にスマートフォンやゲーム機の長時間利用は、近視進行と密接に関連している可能性が高いです。近い所を見る作業を行う際は次のような点に気を付けましょう。
|
・対象から30cm以上、目を離す
・30分に1回は、20秒以上目を休める
・背筋を伸ばし、姿勢を良くする
・部屋を十分に明るくする
・使用する機器の輝度(明るさ)を適切に調節する
|
 |
引用サイト
児童生徒の近視実態調査について
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2024/attach/mext_01403.html
|
| 2025年9月1日掲載 |
 |
【関連コンテンツ】
・子供の目について〜1.視力と屈折異常
・お子さんが近視と言われたら
・こどもの近視に関連する要因について〜論文紹介
・視力の良くないおこさんが増えてきています
・生徒のみなさんからの質問にお答えします。
|
 |